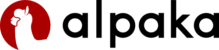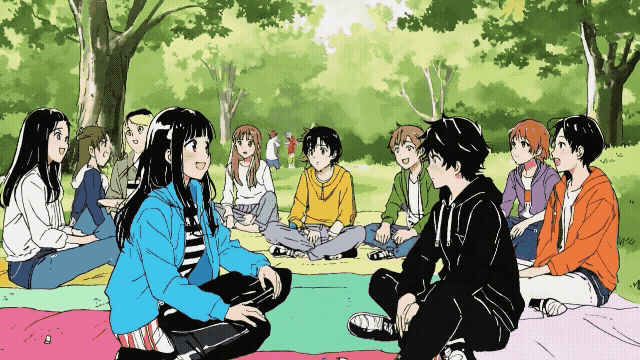Intro: 「界隈」という語は、2020年代以降、SNSを中心に急速に普及した語彙です。元来、地理的な“周辺領域”を指していたこの言葉は、現在では「特定の価値観・趣味・推しへの関心によって緩やかに形成された共同体」を意味する新しい概念として、Z世代を中心に定着しています。本稿では、「界隈消費」という現象を、社会学・メディア論・消費行動論の視座から再定義し、マーケティング戦略における応用可能性を検討していきます。 1. 界隈の構造:フラットかつ流動的な集合性 現代の「界隈」は、従来のコミュニティ概念と異なり、以下のような構造的特徴を持っています: つまり、「界隈」とは、アクティブな発信者とパッシブな受信者の境界が曖昧でありながら、“熱量”によって一時的に凝集する集合体です。Z世代は、この界隈への接続を通じて自我を媒介し、日常的な判断(購買・発信・評価)に反映させています。 2. 界隈消費:消費の物語化と意味 界隈消費は、特定の界隈内部で共有されている記号体系やストーリーに基づいて、モノやサービスを選好・消費する行動です。 この消費行動には、少なくとも以下の4つの特徴が見られます: このような消費は、いわゆる“意味消費”や“文脈消費”の派生形と捉えられ、対象に内在する価値ではなく、関係性の中で生成される意味によって駆動されていると考えられます。 3. SNSと界隈の接続構造:情報流通モデルの再構築 SNS、とりわけTikTokやX(旧Twitter)における情報流通は、従来の“中心-周縁”モデルとは異なり、流動的かつ非対称的です。重要なのは以下の点です: SNSは界隈を可視化するだけでなく、界隈内における「中心的消費者(Core Nodes)」の存在を浮かび上がらせます。これは、インフルエンサーとは異なる“局所的権威者”であり、従来のKOL施策とは異なる設計が必要とされます。 4. 界隈のジャンル類型と産業接続性 2020年代中盤時点において、明確に界隈消費が観測される産業領域は、以下の3つです: a. ファッション b. コスメ c. 食品・スイーツ これらはいずれも、「商品単体」ではなく「消費文脈の設計」が求められる領域です。 5. マーケティングへの含意 界隈消費にアプローチするうえで、マーケティングは以下のような転換を求められます: とりわけ、TikTokなどの短尺動画プラットフォームでは、初速ではなく「語りを引き出す要素設計」「UGCの余白」が重視されます。購買ファネルではなく、「熱狂の波及経路」のマッピングが必要です。 おわり 界隈は、現在のマーケティングにおける“最小にして最大の単位”です。 個人が集団化するのではなく、文脈が人を媒介する構造においては、マーケター自身の観察・読解・翻訳能力が問われます。 界隈消費の理解とは、単に「トレンドを追うこと」ではなく、「意味がどう生成され、どう共鳴し、どう伝播するか」を解剖する試みです。 参考文献・出典